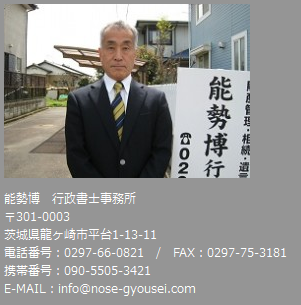相続用語辞典あ行
遺言(いごん・ゆいごん)
自分の死後のことを記した文章。日常会話では「ゆいごん」と言われるが、業界人は「いごん」という。
詳しくは、遺言書作成をご覧ください。
遺産分割
亡くなった方が残した財産を相続人で分割すること。
遺言書があれば基本的にそれに従うが、遺言書が無い場合や、遺言書に具体的な記載がない場合には、相続人全員で分割方法を話し合い「遺産分割協議書」を作成する。
分割の取り分は法定の取り分(妻・子供で1/2づつのように)に従う必要は無く、例えば農地を全て農業承継者に相続させる場合には、遺産分割協議書にその旨書けばよく、相続しない人が相続放棄したりする必要はない。
不動産のように分割が難しいものを、揉めるのを避けるため共有持分で相続するようなケースも見られるが、後々の分割がどんどん難しくなるので、できるだけ全ての財産を単独名義に分割しておいたほうが良い。
相続人に未成年者がいる場合は、裁判所に特別代理人を選任してもらい、協議にはその代理人が加わる。
遺産分割協議書
遺産分割協議した内容を書面に記したもの。
戸籍簿や相続関係図とともに、預金や不動産のの名義変更、受取人指定の無い生命保険金請求などに使う。
捺印は実印を使用し、相続人数分の部数を作成し、それぞれに相続人全員の署名・捺印し、印鑑証明書を添付する。
遺贈(いぞう)
遺言による贈与。
相続人に対しても、相続人以外に対してもできる。
死因贈与と似ているが、死因贈与は贈与者と受贈者との不確定期限契約であるのに対し、遺贈は単独行為である。
遺留分(いりゅうぶん)
法律で認められた相続財産の最低限度の確保できる割合のこと。
遺言で相続人以外の人に財産を譲るという指示がある場合に、相続人の生活権確保の意味合いから配偶者と子供が相続人の場合は財産の1/2、尊属が相続人の場合は財産の1/3を確保できる。
遺留分を確保する請求のことを遺留分減殺請求という。
もちろん、法律に決まりがあるからと言って、絶対にその割合を相続しなければならないわけではなく、たとえばある一人に全財産を相続させ、他の相続人は相続財産がゼロだとしても、相続人が納得すればもちろん有効です。
姻族(いんぞく)
親族の内、配偶者の血族、血族の配偶者と子孫、及び直系尊属の再婚相手とその血族を言います。