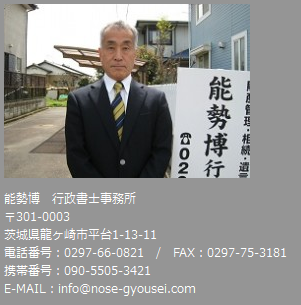相続用語辞典た行
代襲者(だいしゅうしゃ)
亡くなった方の相続人となるべき子供(or孫)が先に亡くなっている場合、その又子供が相続することを「代襲相続」といい、相続する人を「代襲者」もしくは「代襲相続人」と呼びます。
代襲が認められているのは、直系卑属及び兄弟姉妹のみです。しかも兄弟姉妹の場合は、1代限りの代襲しかできません。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続権をもつはずの子供(or孫)や兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その子供が相続することを「代襲相続」といいます。
子供の場合、孫・曾孫と何代にも渡って代襲相続できるのに対し、兄弟姉妹の場合はその子供の代に限られます。
一方、親が相続権を持つ場合、親が亡くなっていて祖父母が生きていた場合は、祖父母に相続権が行きますが、これは代襲ではありません。
例えば、両親の内、父親が亡くなっていて父親の両親は健在だった場合、母親が健在ならば母親だけが相続し、祖父母に相続権はありません。
代襲というと、この場合、母親と父親の祖父母も相続人になることになりますが、実際はそうではありません。
単純承認
相続承認のうち、財産負債の全部を相続すること。
これに対し、限定承認というと、財産の範囲内で負債を相続する旨宣言すること。
仮にうっかりでも相続財産に手をつけると単純承認したことになり、相続放棄できなくなります。
保険金の受取人の指定の無い生命保険は相続財産です。(みなし財産ではありません)
ですから、そういう保険金の請求をすると単純承認したことになり、何百億円の負債があったとしても全額支払わねばなりません。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
結婚届けを出している夫婦の間にできた子供。
結婚中もしくは離婚後300日以内に生まれた子供は、父親が違っていても、嫡出否認または親子関係不存在の訴えが認められるまでは嫡出子とみなされる。
これ以外の子供は非嫡出子であるが、非嫡出子が父親の財産を相続する為には、父親に認知してもらう必要がある。
又、嫡出子と共同で相続する場合は、昔は嫡出子の1/2の取り分でしたが、法改正で現在は嫡出子と非嫡出子の取り分は同じです。
等親(とうしん)
親等の慣用句。詳しくは親等をご覧ください。
特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)
亡くなった人から生前もしくは遺言で、結婚費用・養子縁組費用・学費・結婚資金・住宅資金などで特別な援助を受けていた人が相続人の中にいる場合、その人を特別受益者と言います。
相続財産を分割する場合、その援助分も相続財産とみなして計算し、特別受益者の取り分から援助分を差し引いた額とします。これを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益の持ち戻しをしないよう遺言を残すこともできます。