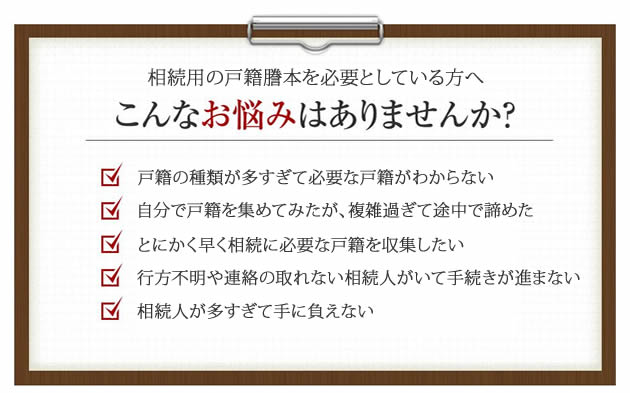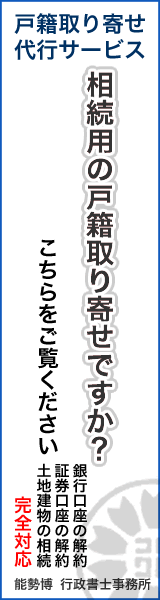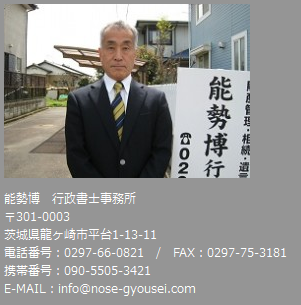戸籍用語辞典か行
改製
法律の改正により、戸籍を作り変えること。
直近では、平成6年からコンピュータ化された横書きの戸籍が作られるようになったのが、最も新しい改製。
現在コンピュータ化の最中なので、役所によっては古い縦書きのままのところも結構ある。
その前の改製は昭和23年からつくられたもので、夫婦子供が1単位の戸籍になった。
その又前の改製は大正4年から作られたもので、戸主とか家督相続とか、最近では聞きなれない言葉がでてきます。
明治時代にも何度か作り直されていますが、最近ではあまりお目にかからなくなりました。又、役所に請求しても昔は保存期間が50年しかなかったので、保存期間が過ぎて廃棄されている場合もあります。
今は保存期間が150年になりましたので、祖父祖母の代くらいであれば廃棄されることは無いでしょう。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
読み方は「かいせいげんこせき」なのですが、「現戸籍」と間違いやすいので、一般的には「はらこせき」と呼ばれています。
改製される前の戸籍のことです。
平成改製原戸籍というと、戦後につくられた最もなじみ深い縦書きの戸籍のことです。
昭和改製原戸籍というと、戦前の「戸主」「家督相続」が出てくるバージョンのことです。
なぜ改製原戸籍が必要になるかというと・・・
新しい戸籍に書きかえられる項目が限られているからなのです。
例えばAさんの前の戸籍の記載事項には、Bさんと結婚しCさんが生まれ、その後BさんはCさんを連れて離婚し、その後Dさんと再婚しEさんが生まれ、Dさんとは死別してEさんは結婚したとします。
このAさんの戸籍が改製されると、新しい戸籍にはBさんCさんDさんEさんは全く記載されないのです。
もしAさんが亡くなると、CさんEさんには相続権がありますが、現在の戸籍だけを見ていてもCさんEさんの存在に気付かないことになります。
それを防ぐために、Aさんが子供を作れる年令まで遡った全戸籍を追っかけて確認する必要があるのです。
家督相続(かとくそうぞく)
「家督」とは「戸主たる地位」のことです。
戸主が死亡したり隠居したりすると、その「戸主たる地位」を長男に引き継がせねばなりません。
それが「家督相続」です。家督相続が起きると戸主が書きかえられる為、戸籍が作り替えられます(戸籍の編成)。
現在は戸籍筆頭者が死亡しても、その戸籍に家族が残っていれば戸籍はそのまま使われますが、戦前は作り変えられたのです。
現戸籍(げんこせき・現在戸籍)
現在の戸籍です。パスポート申請や入社時に提出させられるのはこれです。本籍地の役場で450円で発行してもらえます。
戸主(こしゅ)
家の代表者のこと。家族の統卒・監督権限をもち、扶養義務を負っていた。
権限はかなり強力で、家族の結婚同意や子供の勘当、家族を除籍する権利などを持ち、財産も全て相続した。
個人事項証明書
以前の戸籍抄本にあたる言い方。
現在のコンピュータ化された戸籍で、家族全員の写しが全部事項証明書。ある1人だけの写しが個人事項証明書。
戸籍(戸籍簿)
夫婦子供単位で国民を登録する為の公文書。戸籍法に定めがある。
日本国籍を証明する唯一の公的証書。
出生・氏名・婚姻・子・養子縁組・国籍離脱等の身分関係を明確にし、婚姻・離婚の届出やパスポート発行手続きが容易にできる。
相続人特定に欠かせない資料である。
戸籍事項欄
その戸籍全体の、作られた日(編成日)、抹消された日(消除日)、転籍日及び従前の本籍地などが記載される。