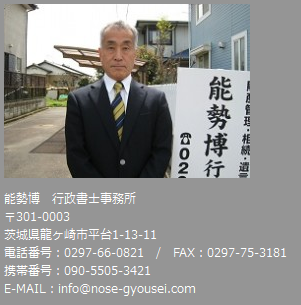取り扱い対象としての「法令」
「法令遵守」と言っても対象となる法令はいったいどんなものがあるのでしょう?大きく分けて全ての会社に適用される法令と、業種ごとによって異なる法令の2種類があります。
まず、全ての会社に適用される法令には以下のようなものがあります。
1.共通法令
- 憲法
- 基本的人権の尊重・職業選択の自由・勤労の権利義務・納税義務など
- 会社法
- 取締役及び株主総会の義務・会計原則など
- 法人税法
- 納税義務
- 労働基準法
- 労働者の権利擁護
- 独占禁止法
- 公正自由な競争の促進
- 不正競争防止法
- 知的所有権の確保
- 消費者保護法
- 消費者の保護・契約の取消権など
- 個人情報保護法
- 個人情報の管理責任
- 製造物責任法
- 製造物の欠陥による損害賠償責任
次に業種ごとによって異なる法令があります。
2.業種ごとの法令
- 建設業界
- 建設業法・品確法
- 運輸業界
- 道路運送法・道路運送車両法
- 不動産業界
- 宅建業法・建築基準法・都市計画法
- 医療業界
- 医師法・薬事法
- 食品業界
- 食品安全基本法・食品衛生法
- 証券業界
- 金融商品取引法
これらはほんの一部分を列記したにすぎません。
これらの法令に違反すると罰則の対象となり、又、法令の規定により行政機関より業務に関する許認可を受けている場合は、許認可の取消処分を受けたり、業務停止命令を受けたりと、所謂行政処分を受けることもあります。そうした場合、マスコミ報道されることもありますし、そうなれば広く世間に知られることになり、大きな信用失墜に至ることになります。そうした意味で、法令はコンプライアンス上の重要な要素であると言えます。
取り扱い対象としての「社内規則」
社内規則が必要なのは、「法令」を守るための具体的なルールが社内に無いと、どうしたら法令を守れるのかが不明確になってしまうからです。「法令」には全ての会社に適用されるものと、業界ごとに異なるものとがありますが、その対象数が大変多く、又それぞれの法令に書かれている内容も非常に広範囲にわたります。
全ての社員が全ての法令に書かれていることを熟知し、業務中に常に意識できていれば良いのでしょうが、それは実際問題不可能なことです。又、法令の文章は理解しにくく、一般の人にとっては読むことすら苦痛なものです。そこで、直接法令に触れなくとも、法令違反にならないような分かりやすい「社内規則」を定めて身近に置いておく必要があります。「社内規則」には、規程・マニュアル・作業手順書・社内通知文などの呼び名で、多くの種類があります。一般的には業務に関する基本原則的なものを「規程」に定め、「規程」に書かれていることをより具体的な言い方に代えたものが「マニュアル」「作業手順書」となり、規程やマニュアル類を修正せずに随時微調整したり、最新の対応ルールを定めたりするものが「社内通知文」となっていることが多いようです。
社内規則には以下のようなものがあります。
- 会社の基本規則
- 定款・株主総会規程・取締役会規程・組織規程・業務分掌規程・倫理綱領・個人情報保護宣言
- 会社の基本的運用に関する規則
- 就業規則・経理規程・資産管理規程・広報規程
- 情報管理に関する規則
- 情報管理規定・個人情報保護規程・入退室マニュアル
- 業務に関する規則
- 業務取扱規程・在庫品管理規程・接客マニュアル
これらの社内規則は分かりやすい文章で書かれていることが絶対原則です。社内規則が法令と同じような理解しにくい文章で書かれていたら、そもそもそんな規則は必要なく、結局社内全体に趣旨が浸透せず、結果的に法令違反を引き起こす原因になるかもしれません。
取り扱い対象としての「倫理」
倫理は会社の基本的な考え方を表したもので、社是・倫理綱領・規範などと呼ばれます。
「会社の業務を通じて社会に貢献する」とか、「お客様第一主義」「三方よし経営」など、営利企業といえども金を稼ぐことが全てではなく、人様のお役に立つ、社会のルールを守るなど、会社が社会組織の中で心がけるべき事柄が書かれています。「法令」⇒「社内規則」⇒「倫理」となるにつれ、明確な規則⇒物事の考え方にウェイトが移っていきます。
具体的に考えてみましょう。
田舎町の古い商店街を1本の道が通っています。制限速度40㎞の道路標識が立っています。めったに車も通らないので子供たちが鬼ごっこをして遊んでいます。そこへあなたが営業車で通りかかりました。
あなたはどうしますか?
- ①40㎞で通り抜ける。
- 道路交通法上の速度制限にも違反していませんし、事故がなければ何のお咎めもないでしょう。一般的にはこのケースが多いと思います。(安全運転義務違反ですね)
- ②30㎞にスピードを落として通り抜ける。
- 法令の規制より厳しく対応しました。法令で許されているからよいという考え方からは一歩踏み込んで、安全に対する意識をより強く対応しています。「社内規則」の考え方です。
- ③子供たちの前で一時停止し、子供たちの注意を促してから横を徐行して通り抜ける。
- 「倫理」の考え方です。何が大事かを自分で考え、社会の為になる、社会に迷惑を掛けない行動をとるのは倫理的思考です。もしかしたら、見通しの良い大平原の一本道を80㎞で走ることがあるかもしれません(お勧めはしませんが・・)。規則の枠を超え、自己責任で対応する意識が「倫理」の意識です。